AWS 導入事例
経済産業省 様
GXリーグの運営を支える システムと IaC 活用による環境構築の最前線
2025/08/18
GXリーグは、2050年の カーボンニュートラル実現と 社会変革を見据えて、GX(グリーントランスフォーメーション)への挑戦を行い、現在 および 未来の 社会における 持続的な成長の実現を目指す企業が、同様の取り組みを行う企業群や 官・学と協働する プラットフォームです。
今回、株式会社野村総合研究所(以下「NRI」)は、Infrastructure as Code (IaC)技術を活用し、GXリーグの活動を支える プラットフォームの システム開発を行いました。この取り組みについて、GXリーグの システム構築を担当した NRI の 川口 直輝と プロジェクトマネージャーの 大中 太郎、IaC 導入を進めた 平野 裕昭、八十田 周作から、IaC を採用した背景と効果を交えて ご紹介します。

- 写真左から、野村総合研究所(NRI)の 八十田 周作・川口 直輝・大中 太郎・平野 裕昭。
背景とプロジェクトの成り立ち
日本の脱炭素社会を加速する GXリーグの誕生と
産学官連携で築く 画期的プラットフォームの開発
- GXリーグの システムは、どのような機能や特徴を持っているのでしょうか? また、プロジェクトの基本的なコンセプトについて 詳しく教えていただけますか?
大中: まず初めに GXリーグについて説明します。国は 2050年までの カーボンニュートラル実現を目標として掲げており、その達成に向けて 産学官が連携して 温室効果ガスの排出量の削減に取り組んでいます。GXリーグは、経済産業省の主導により、カーボンニュートラルを企業の成長機会と捉え、環境配慮と事業成長の両立を目指す企業が集まる プラットフォームとして 設立されました。NRI は、この GXリーグの事務局運営を担当するとともに、活動を支えるための システム構築も担っています。
GXリーグの システムは、カーボンニュートラルの実現に向けた企業の取り組みを「見える化」し、目標設定から 実績報告まで 効果的に管理できる仕組みになっています。参加している企業が 2050年の カーボンニュートラル実現に向けて どのような目標を立て 温室効果ガス削減に取り組んでいるのか、具体的な取り組み内容や 年度ごとの実績を 登録・管理できます。現在、GXリーグには 500社以上が参加しており、企業ごとの情報を 一元管理しています。システムは Webアプリケーションとして提供されており、企業は インターネット経由で アクセスし、自社の状況を入力しながら 効率的に進捗管理を行うことができます。
川口: 今回の議題でもある IaC とも関連し、システムの基盤面の設計において 特に意識したのは セキュリティ面です。今回、構築したのは GXリーグ公式サイトの サブシステムにあたる 企業向けの Webアプリケーションです。GXリーグ公式サイトの ダッシュボードには 各企業の取り組み内容、CO2 排出量などの情報が開示されていますが、私たちが構築した システムは、一部公開できない企業の 重要情報を扱う システムであるため、国家サイバー統括室(旧:内閣サイバーセキュリティセンター)が定める「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に準拠し、通信の暗号化や 情報漏洩防止策を 徹底しました。この インフラ基盤に IaC 技術を活用し、安全 かつ 効率的に運用できる環境を 整理しています。これによって、企業の大切な データを守りながら、信頼性の高い システムとして 運用を続けられています。
- プロジェクトが立ち上がった背景や 直面した主な課題は 何でしょうか?
川口: GXリーグ自体は 2030年に向けて 複数のフェーズに分かれているのですが、私たちの システム構築の プロジェクトは 2023年度から 2024年度にかけての フェーズで進められました。プロジェクト期間中には、実際に GXリーグ参画企業が利用する「本番環境」だけでなく、開発工程で利用する検証環境や、事務局が業務フローを確認するための UAT (User Acceptance Test、受け入れテスト)環境など、工程ごとに応じた 適切な テスト用の環境を整備していく必要がありました。
また、プロジェクトとしても GXリーグの 試行フェーズにあたる期間のため、最初から確定した要件があるわけではなく、制度設計の詳細を詰めながら それに合わせた システムを構築する必要があるといった背景もあったことから、要望や工程の変化に柔軟に対応しつつ、環境構築の スピードを上げていくことも 課題の 一つでした。こうした要望を受けて、プロジェクト途中で システム構築チームと相談を重ね、IaC を活用した 柔軟な環境構築の検討が 始まりました。
- IaC の技術獲得は どのような背景から進められたのでしょうか? また、技術を活かす上で 意識している ポイントは ありますか?
平野: IaC の技術獲得は、AWS 環境での システム構築を手作業で行っていた経験から 効率化の必要性を感じたことが 背景にあります。2016 ~ 17年頃、当初は 手作業で工数をかけて環境を構築していましたが、新規案件ごとに環境を 構築・破棄する作業の コスト負荷が高まっていました。
そのような中、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK、AWS クラウド開発キット)という ツールの存在を知り、自分自身の AWS 学習用として使いはじめたのが 活用の きっかけです。データベースや Webサーバー、WAF (Web Application Firewall)などを AWS CDK で定義しておき、必要な時に起動、不要になれば削除することで、環境の作成と破棄を効率化でき、これを活用すれば、環境構築に多くの人手がか かっている問題を 解決できると感じました。その後、私が個人的に取り組んでいたノウハウや R&D (Research and Development、研究開発)の成果も含め、チームと共に AWS CDK の ガイドラインを作成して 社内に公開し セミナーで発表したことを きっかけに、今回の システムに導入できないか 相談を受けました。
AWS CDK を実装する上で意識したのは、「分かりやすい構造にすること」です。GXリーグ向けに AWS CDK 開発を行う際にも、ディレクトリ構造を シンプルに標準化し、コードの格納場所を決めています。利用者からも「ソースコードの構造が分かりやすい」と 高評価を受けました。もう一点は、「無理に複雑な仕組みを作り込まないこと」です。TypeScript 版の AWS CDK を活用しているので 自由度が高く コーディングすることが できるのですが、AWS CDK の 公式マニュアルに沿った使い方を心掛けていて、過度に機能を詰め込みすぎず シンプルにすることを 意識しています。

- 野村総合研究所(NRI)の 平野 裕昭。
導入の概要・ポイント
手作業から コード管理へ。IaC 活用で実現した 柔軟 かつ 高速な環境構築
- AWS CDK を選んだ理由や そのメリットについて 詳しくお話しいただけますか?
八十田: AWS CDK を採用した理由は「コードの簡潔さと 可読性の高さ」です。従来の IaC ツールでは、AWS の リソースを定義するのに YAML 形式を使うことが多いのですが、リソースの定義に対して 長いコード行数が必要でした。一方、AWS CDK は 抽象化が進んでおり、YAML で 100行程度必要だった記述を十数行で実装可能です。また、AWS CDK は プログラミング言語を ベースにしているため、テストコードの作成が可能で、自動化や品質保証の面でも優れているという メリットもあります。こうした可読性の高さや 拡張性の良さが、AWS CDK を 選ぶ理由となりました。
- IaC 導入にあたっての ポイントや 注意点について 教えてください。特に、プロジェクトにおいて どのような施策を講じましたか?
川口: IaC 導入にあたっては 大きく 2つの ポイントがありました。まず、導入後の運用を見据えた実装です。単に 1つの環境を コード化するのではなく、本番環境と開発環境では 求められる要件が異なるため、それらを パラメータで 切り替えられるようにしています。ベースとなる コードは 1つですが、環境ごとに 一部 異なる設定を 簡単に管理できる構成にすることが 重要でした。そういった設計は、平野さんを中心に AWS CDK の ガイドラインを公開した チームである xPalette (クロスパレット)が提供する コードで 最初から考慮されており、大変 助かりました。環境によって異なる要件を パラメータにすることで 環境の差分を明確にしつつ、全体としては 1つの コードとして管理することで、導入後の運用、メンテナンスの負荷を 軽減することができました。
もう 1つは 初期構築時の 開発の アプローチです。もともと途中までは 私たちも手作業で環境を作っていたので、今回の IaC 導入においては 設計書に基づいて コードを書くのではなく、既に構築されていた実績のある環境を基に、どうすれば同じ環境を コードとして再現できるかを逆算して 開発を進めました。この方法により、期待される結果が明確になっている状態で構築を行うことができたため、品質面でも良好な結果が得られたと感じています。

- 野村総合研究所(NRI)の 川口 直輝。
平野: 既存の テスト環境を複製したいという ニーズがあり、「いかに既存の環境をコードに反映するか?」が 重要なポイントでした。最初、私たちが取り組んでいたのは、何もない環境に対して ある程度の設計をして環境を作るという形の作業でしたが、今回は既にある環境を コード化する必要があり、それが難しい点でした。そこで、Former2 という、AWS 環境をスキャンし AWS CDK コードに変換する オープンソースソフトウェアを使用しました。xPalette の標準化と組み合わせながら 試行錯誤を繰り返した結果、問題なく動作する コードを完成させることができました。現在は より良いツールもあるかもしれませんが、当時は十分に効果的だったと感じています。
八十田: AWS CDK プロジェクトの初期段階では ディレクトリ構成が分かりづらく、特に新しく参加する メンバーにとっては 理解しにくいものでした。そこで、新規参画者や初学者が迷わないように、ディレクトリ構成を より分かりやすく整理する工夫を行いました。また、AWS リソースの命名規則や 環境ごとの パラメータは既に決まっているため、開発者が ソース上に 個別に設定をするのではなく、プロジェクトで横断的に使用する関数を共通化して 簡単に利用できるようにしたことも ポイントです。さらに、ソースコードだけでなく、何を作成しているかを明示する ドキュメントを整備し、コードの目的や構造を 誰でも理解できるようにしています。
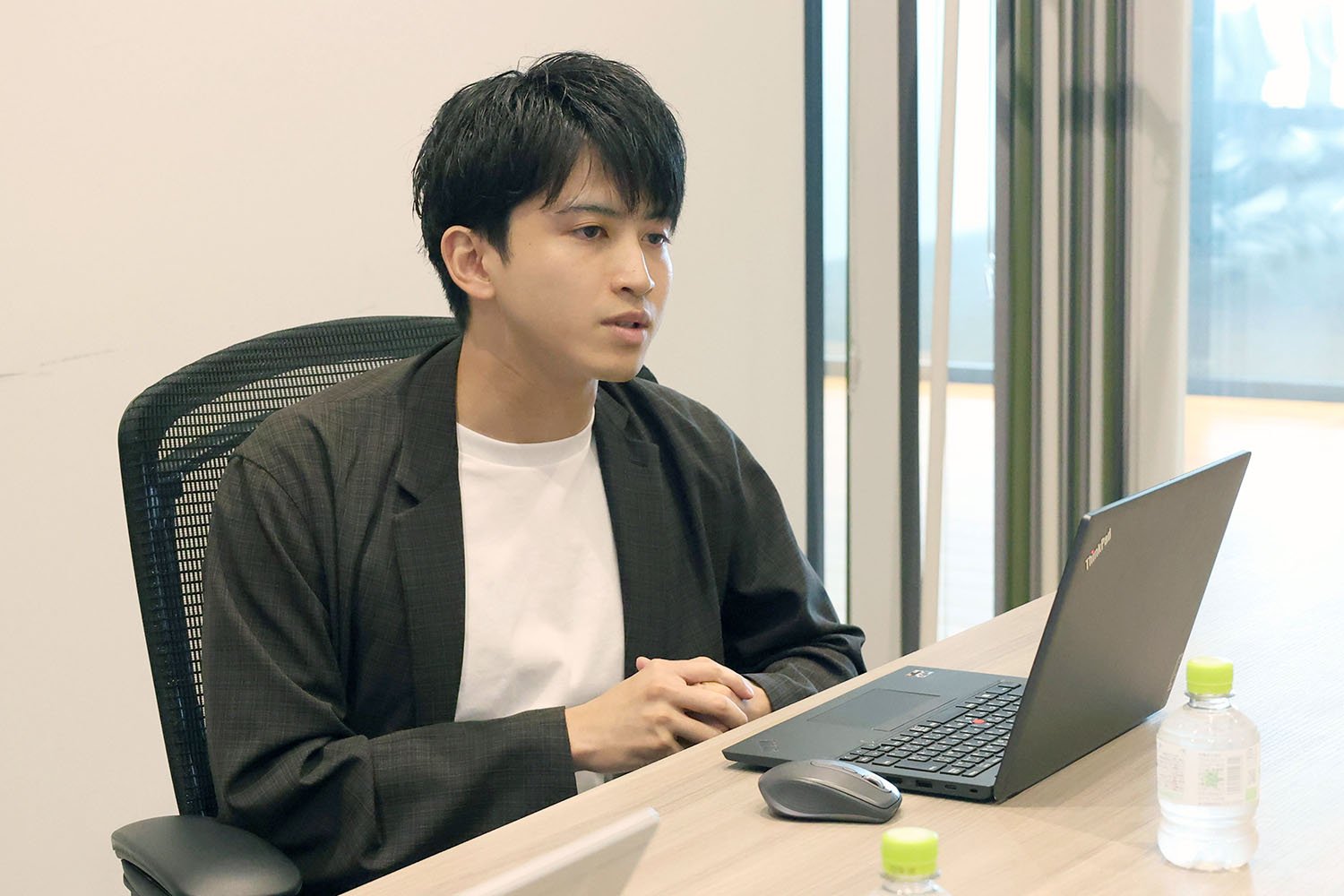
- 野村総合研究所(NRI)の 八十田 周作。
導入の効果、今後の展望
環境構築のコストや時間が激減! IaC 活用で実現した 効果と未来展望
- IaC を導入することにより、具体的に どのような効果や成果が得られましたか? プロジェクトに与えた インパクトについても お聞きしたいです。
川口: IaC を導入する前は、手作業で環境を構築していたため、多くの時間がかかり、人為的な手順ミスや リスクも存在していました。また、手順書を作成して同じ作業を繰り返すという形で 再現性を保っていましたが、それでも ミスが完全に なくなるわけでは ありませんでした。
IaC 導入後は、環境ごとの パラメータを変更するだけで ほぼ自動的に環境構築が完了します。その結果、環境作成にかかる時間や コストが 大幅に削減され、手順書の必要性も減りました。システムの規模や環境差異となる範囲の大きさにもよりますが、システム基盤の初期構築にかかる時間は、手作業で行っていたころと比較して、構築後の確認や手順書の管理にかけていた時間も含めると、おおよそ 7割程度は削減できたのではないかと思います。
また、今回の システムは インターネットからの アクセスを前提として セキュリティ強化された基盤環境を構築しています。サブネットの構成や、WAF、ファイアウォール、セキュリティグループなど、考慮すべき ポイントの 基本的な セットアップが コードとして蓄積されていることは、設計書や手順書として蓄積することに比べて 運用・開発面で 大きな メリットがあります。
平野: AWS の クラウド環境における システム設計と運用の品質を評価するための、AWS 公式の指針「AWS Well-Architected」があります。「AWS Well-Architected」の フレームワークで 一般的な設計原則として「本稼働スケールで システムを テストする」というものがあるように、本番と同じ規模の環境を テスト環境として作成し、テスト終了後に破棄できるのは IaC ならではの 強みです。これは GXリーグの環境構築の中で まさに体験していただいていると感じています。手作業では実現困難だったことが、自動化により可能となりました。また、一度コードで作った環境に 新機能を追加したり、一部機能を外して 別の システムを作ったりと、ソースコードの世界で 柔軟に対応できる点も 大きな メリットです。こうした 運用の スピード感や柔軟性は、手作業にはない利便性を もたらしています。

- 写真左から、野村総合研究所(NRI)の 川口 直輝・平野 裕昭・八十田 周作。
- GXリーグの 今後の展開について、どのように考えていますか?
川口: GXリーグは 2023年度から 2025年度まで 試行期間の フェーズを経て、2026年度以降に カーボンニュートラルに向けた 本格的な活動が始まります。新システムにより 排出量取引の仕組みが導入され、企業による カーボン削減量の売買が可能になります。NRI としては引き続き GXリーグの本格活動の流れに 積極的に関わりたいと思っています。
今回、構築した システムや ナレッジは、本格稼働の フェーズでも活かせると 考えています。また、2025年度に リリースした システムは、IaC を用いて 本番環境を構築していますが、一度の開発と リリースで終わりではなく、維持保守や 新規案件への展開も 重要です。システムの構造や コンセプトを維持しつつ、継続的に 改善・強化していくことを目指しており、それが IaC を導入することの 最大の メリットでもあると 考えています。
- IaC 活用に関する 今後の活動について、将来的な計画や ビジョンを 教えてください。
平野: 今後は、プロジェクトの初期段階から クラウド基盤の プロトタイプを AWS CDK で 構築してみる、という取り組みを 考えています。システムの概要が ある程度 分かった段階で 環境を作り、お客様の ニーズを聞きながら ソースコードを更新して要件を反映、設計完了時には基盤環境も完成している、という理想的な開発サイクルを 実現したいと思っています。
八十田: IaC の価値を高める取り組みとして、クラウドを構築する際に IaC の段階から セキュリティ面の担保を図りたいと 考えています。現在、市場には 様々なツールがありますが、IaC と セキュリティスキャンツールを組み合わせるような動きが 重要になってくると思っています。
カスタマープロフィール

経済産業省
経済産業省は「未来に誇れる日本をつくる。」というミッションのもと、世界が直面する社会課題の本質に真摯に向き合い、日本を豊かにするための政策を担っています。

GXリーグ
2050年の カーボンニュートラル実現と 社会変革を見据えて、GX への挑戦を行い、現在 および 未来社会における 持続的な成長の実現を目指す企業が、同様の取組を行う企業群や 官・学と共に協働する場が、GXリーグです。
関連する AWS の 製品、ドキュメント
Infrastructure as Code (IaC)
Infrastructure as Code (IaC)とは、手動の プロセスや 設定の代わりに コードを使用して コンピューティングインフラストラクチャを プロビジョニング および サポートできることを言います。どのような アプリケーション環境であっても、オペレーティングシステム、データベース接続、ストレージなどの 多くの インフラストラクチャコンポーネントが 必要です。デベロッパーは、アプリケーションを 開発、テスト、デプロイするための インフラストラクチャを 定期的に 設定、更新、メンテナンスする 必要があります。
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK、AWS クラウド開発キット)は、コードで クラウドインフラストラクチャを定義し、 AWS CloudFormation を通じて プロビジョニングするための オープンソースの ソフトウェア開発フレームワークです。
AWS Well-Architected
AWS Well-Architected は、クラウドアーキテクトが 様々な アプリケーションや ワークロード向けに 高い安全性、性能、障害耐性、効率性を備えた インフラストラクチャを構築する際に 役立ちます。AWS Well-Architected では、6つの柱(優れた運用効率、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、コストの最適化、持続可能性)に基づいて、お客様と パートナーが アーキテクチャを評価し、スケーラブルな設計を実装するための 一貫した アプローチを 提供しています。
関連リンク・トピックス
・atlax / クラウドの取り組み / AWS(Amazon Web Services) ※カテゴリーTOPページ
・atlax / ニュース・トピックス / 「AWS」カテゴリー の 記事一覧
・atlax blogs / 「AWS」カテゴリーの 記事一覧 ※ atlax blogs サイトへ
・2022/03/08 野村総合研究所、経済産業省の「GXリーグ基本構想」に賛同 ※NRIサイトへ
NRI の AWS 導入事例・特別対談
-

野村総合研究所(NRI)は、AWS プレミアティア サービスパートナーです。多数の顧客エンゲージメントや 幅広い経験、顧客との フィードバックや サクセスストーリーの収集を通じて、2013年に 日本で初めて認定されて以降、12年連続で AWS プレミアティア サービスパートナーに 認定されています。
また NRI は、「AWS 金融サービス コンピテンシー」 「AWS DevOps コンピテンシー」 「AWS 生成 AI コンピテンシー」 「AWS MSSP コンピテンシー」 「AWS 移行 コンピテンシー」 「AWS セキュリティ コンピテンシー」 「AWS Oracle コンピテンシー」 「AWS SAP コンピテンシー」を取得しており、コンサルティング、システム開発・運用、アナリティクス、生成 AI といった 幅広い分野で、お客様の課題解決に AWS を活用し、ビジネス推進を サポートしています。

